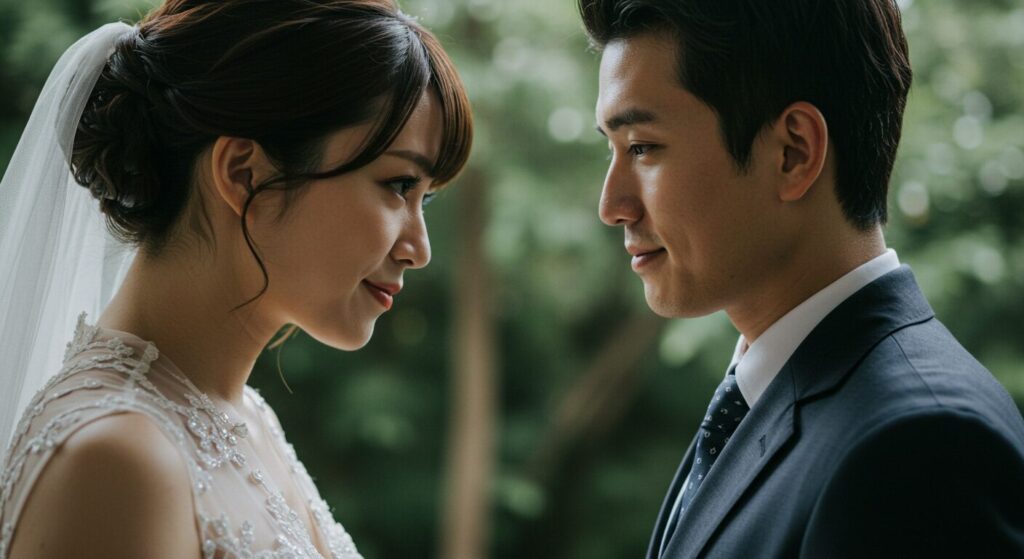
夫婦関係が悪化し、別居に至った場合、多くの方が直面するのが婚姻費用の問題です。
「婚姻費用を払わなくていい場合があるのだろうか」、あるいは「婚姻費用をもらえないケースとは具体的にどのような状況なのか」といった疑問は尽きません。
また、同意のない別居と婚姻費用の関係や、実家暮らしと婚姻費用の算定方法、そして基準となる婚姻費用算定表の正しい理解も重要です。
支払いが滞れば、婚姻費用を払わない場合の差し押さえという厳しい現実や、未払い婚姻費用の一括請求といった事態も起こり得ます。
中には、婚姻費用を払いたくない時の離婚という選択肢を考える方もいるかもしれません。
しかし、安易な判断は、時に「婚姻費用の地獄」とも言えるような深刻な状況を招きかねません。
この記事では、これらの複雑な婚姻費用の問題について、基本的な知識から具体的な対処法まで、分かりやすく解説していきます。
婚姻費用を払わなくていい場合:その条件と法的根拠

婚姻費用の基本と支払い義務
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な一切の費用を指します。
具体的には、日常の食費、住居費、水道光熱費、医療費、未成熟子の養育費などが含まれます。
日本の民法第760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。
これは「生活保持義務」と呼ばれ、夫婦は互いに自分と同じ水準の生活を相手にも保障する義務があるという意味です。
この義務は、夫婦が法的に婚姻関係にある限り継続するため、たとえ別居している状態であっても、原則として婚姻費用を分担する義務はなくなりません。
通常、収入の多い方の配偶者が、収入の少ない方の配偶者に対して、生活費として婚姻費用を支払うことになります。
この支払いは、夫婦双方の収入や資産、社会的地位など、あらゆる事情を総合的に考慮して公平に分担されるべきものとされています。
もし夫婦間での話し合いで金額や支払い方法が決まらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決定を求めることになります。
この婚姻費用の分担義務は、夫婦である以上負うべき法的な責任であり、一方的な理由で支払いを拒否することは原則として認められません。
したがって、婚姻関係が継続している間は、お互いの生活を支え合うという基本的な考え方が根底にあります。
婚姻費用をもらえないケースとは?
婚姻費用は原則として夫婦間で分担されるべきものですが、例外的に支払いが免除されたり、請求が認められなかったりするケースが存在します。
その一つが、請求する側に夫婦関係を破綻させた主な原因がある「有責配偶者」と認められる場合です。
例えば、不貞行為(浮気や不倫)を行った側や、相手に対して暴力(DV)やモラルハラスメントなどを行い、それが原因で別居に至った場合などです。
このような場合、有責配偶者からの婚姻費用の請求は、信義誠実の原則に反する、あるいは権利の濫用にあたるとして、裁判所が請求を認めないか、大幅に減額することがあります。
ただし、夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、子どもの養育にかかる費用については、親としての責任があるため、有責配偶者であっても相手に請求できるのが一般的です。
また、夫婦には同居し、互いに協力し扶助する義務(同居義務・協力義務・扶助義務)があります。
正当な理由なく一方的に家を出て別居を開始し、同居義務に違反していると判断される場合も、婚姻費用の請求が制限されることがあります。
例えば、夫婦関係に大きな問題がなかったにもかかわらず、相手に無断で、あるいは話し合いに応じずに勝手に家を出て行ったようなケースです。
さらに、婚姻費用の支払いについて夫婦間で具体的な取り決めがなく、かつ相手方から明確な請求がされていない期間については、遡って支払う義務が生じないこともあります。
その他、例外的なケースとして、請求する側が別居時に夫婦の共有財産から不相当に高額な金品を持ち出した場合なども、公平性の観点から婚姻費用の支払いが調整される可能性が考えられます。
同意のない別居と婚姻費用の関係
夫婦の一方が相手の同意を得ずに別居を開始した場合、婚姻費用の支払いに影響が出ることがあります。
夫婦には民法で定められた同居義務がありますが、同意のない別居が直ちに同居義務違反となり、婚姻費用の請求権が失われるわけではありません。
重要なのは、別居に至った経緯や理由です。
例えば、相手からのDVやモラルハラスメントから逃れるために緊急避難的に別居した場合や、相手の不貞行為が原因で精神的に同居を続けることが困難になった場合など、別居に正当な理由があると認められれば、同意がなくても婚姻費用の請求は正当なものとして扱われる可能性が高いです。
このようなケースでは、むしろ別居の原因を作った側(有責配偶者)が婚姻費用を支払う義務を負うことになります。
一方で、特に正当な理由なく、一方的な意思で身勝手に家を出て同居を拒否しているような場合には、同居義務違反と判断され、婚姻費用を請求する権利が制限されたり、減額されたりする可能性があります。
この場合、別居された側は、婚姻関係の破綻について責任がない、あるいは責任が小さいと主張できるためです。
裁判実務では、同意のない別居であっても、それが「悪意の遺棄」に該当するかどうかが一つの判断基準となります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を放棄することを指し、これに該当すると判断されれば、婚姻費用の請求は権利濫用とみなされることがあります。
したがって、同意のない別居における婚姻費用の問題は、単に同意の有無だけでなく、別居に至った具体的な事情や、どちらに夫婦関係破綻の原因があるかなどを総合的に考慮して判断されます。
実家暮らしと婚姻費用の算定
夫婦の一方または双方が別居後に実家で暮らす場合、それが婚姻費用の算定に影響を与えることがあります。
婚姻費用は、夫婦双方の収入や生活状況に応じて公平に分担されるべきものです。
権利者(婚姻費用を受け取る側)が実家に戻り、親族の援助を受けて生活している場合、住居費や水道光熱費などの生活コストが通常よりも低く抑えられる可能性があります。
このような場合、義務者(婚姻費用を支払う側)は、権利者の生活費が軽減されていることを理由に、婚姻費用の減額を主張することが考えられます。
ただし、実家暮らしであるという事実だけで自動的に婚姻費用が大幅に減額されるわけではありません。
裁判所は、実家からの経済的援助の具体的な内容や程度、権利者自身の収入状況、そして子の有無や年齢などを総合的に考慮して判断します。
例えば、権利者が無職で、実家からの援助がなければ生活が困窮するような状況であれば、減額幅は小さくなるか、あるいは考慮されないこともあります。
逆に、義務者側が実家暮らしである場合、自身の生活費が抑えられることで、婚姻費用の支払能力が高まると見なされる可能性も理論上は考えられますが、婚姻費用の算定は主に双方の収入に基づいて行われるため、この点が直接的に増額事由となることは少ないでしょう。
むしろ、義務者の収入が安定しており、支払能力に余裕があると判断される一要素となる程度です。
婚姻費用の算定においては、標準的な生活費を基準としつつも、個別の事情が考慮されます。
そのため、実家暮らしという状況が婚姻費用に与える影響はケースバイケースであり、具体的な生活実態や経済状況を明らかにした上で、公平な分担額が決定されることになります。
婚姻費用算定表の正しい理解
婚姻費用算定表とは、夫婦双方の収入や子の人数・年齢に応じて、標準的な婚姻費用の月額を簡易迅速に算出するために、裁判所の実務で広く用いられている目安表のことです。
この算定表は、過去の多くの事例や統計データに基づいて、東京と大阪の裁判官が中心となって作成したもので、家庭裁判所における調停や審判で婚姻費用を決定する際の参考資料として活用されています。
算定表は、夫婦双方の年収(給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額、自営業者の場合は確定申告書の所得金額などが基準となります)と、14歳以下の子と15歳以上の子の人数によって、複数の表に分かれています。
該当する表を見つけ、縦軸と横軸からそれぞれの収入に対応する箇所を探すことで、おおよ目の婚姻費用の金額帯を把握することができます。
しかし、この算定表で示される金額はあくまで標準的なケースを想定した目安であり、法的な拘束力を持つものではありません。
個別の事情によっては、算定表の金額から増減されることがあります。
例えば、子どもが私立学校に通っていて高額な学費がかかる場合、夫婦の一方が特別な医療費を必要としている場合、あるいは住宅ローンの負担がある場合などは、算定表の金額に加えて別途考慮されることがあります。
また、権利者(婚姻費用を受け取る側)に働く能力があるにもかかわらず働いていない場合(潜在的稼働能力)、一定の収入があるとみなして算定されることもあります。
したがって、婚姻費用算定表を利用する際は、それが絶対的な基準ではないことを理解し、自分たちの具体的な状況を考慮した上で、適切な婚姻費用の金額を話し合う、あるいは法的手続きの中で主張していくことが重要です。
婚姻費用を払わなくていい場合:未払いのリスクと対処法

婚姻費用を払わない場合の差し押さえ手続き
婚姻費用の支払いは法律上の義務であり、夫婦が合意した内容や家庭裁判所の調停・審判で決定された金額を正当な理由なく支払わない場合、権利者は法的な手段を用いて強制的に回収を図ることができます。
その代表的な方法が「差し押さえ」を含む強制執行です。
まず、婚姻費用の取り決めが公正証書や調停調書、審判書といった債務名義として存在することが前提となります。
これらに基づき、権利者は地方裁判所に強制執行の申し立てを行います。
申し立てが認められると、裁判所は義務者の財産に対して差し押さえ命令を発令します。
差し押さえの対象となる財産は多岐にわたりますが、最も一般的なのは給与や預貯金です。
給与差し押さえの場合、原則として手取り額の4分の1までとされていますが、婚姻費用や養育費といった扶養義務に関する債権については、例外的に手取り額の2分の1まで差し押さえることが可能です。
これは、生活を支えるための費用としての重要性が考慮されているためです。
差し押さえ命令が出ると、義務者の勤務先や金融機関に裁判所から通知が送付され、義務者本人よりも先に知られることもあります。
これにより、義務者は経済的な不利益を被るだけでなく、職場での立場や社会的信用にも影響が出る可能性があります。
差し押さえ手続きは、権利者にとっては最終的な回収手段ですが、義務者にとっては深刻な事態を招くため、支払いが困難な場合は放置せず、速やかに権利者と話し合い、支払い計画の見直しなどを検討することが重要です。
未払い婚姻費用の一括請求について
婚姻費用の支払いが滞り、未払い分が蓄積した場合、権利者はその未払い分全額を一括で支払うよう請求することが原則として可能です。
過去の未払い婚姻費用は、離婚が成立した後であっても請求権が消滅するわけではありません。
最高裁判所の令和2年1月23日の決定でも、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合でも、離婚時までの過去の婚姻費用分担請求権は消滅せず、離婚後も請求できるとの判断が示されています。
未払い婚姻費用の一括請求を行う場合、まずは内容証明郵便などで義務者に対して支払いを求めるのが一般的です。
これにより、請求の意思を明確に伝え、支払いを促す効果が期待できます。
それでも支払いに応じない場合は、家庭裁判所に未払い婚姻費用の支払いを求める調停や審判を申し立てることができます。
既に婚姻費用の取り決めが調停調書や審判書などの債務名義として存在する場合は、これに基づいて強制執行(差し押さえ)の手続きを進めることも可能です。
ただし、未払い婚姻費用の請求権には時効が存在します。
夫婦間の協議で定めた場合は原則5年、調停や審判で確定した場合は原則10年で時効により消滅する可能性があります。
時効の起算点や中断事由など、法的に複雑な要素も絡むため、注意が必要です。
義務者側が経済的に困窮しており、一括での支払いが現実的に不可能な場合は、権利者との間で分割払いの交渉を行うことも考えられます。
いずれにしても、未払い状態を放置することは、遅延損害金が発生するリスクや、法的手続きへ移行する可能性を高めるため、双方にとって早期の対応が求められます。
婚姻費用を払いたくない時の離婚という選択肢
婚姻費用の支払い義務は、法的に婚姻関係が継続していることを前提としています。
したがって、離婚が成立すれば、それ以降の婚姻費用を支払う義務は原則として消滅します。
このため、婚姻費用の負担を避けたいと考える義務者にとって、離婚は一つの選択肢となり得ます。
しかし、この選択には慎重な検討が必要です。
まず、夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、離婚によって婚姻費用の支払い義務はなくなっても、新たに「養育費」の支払い義務が発生します。
養育費は、子どもが経済的に自立するまで必要となる費用であり、その算定基準や支払い期間は婚姻費用とは異なりますが、親としての責任は継続します。
また、婚姻費用を支払いたくないという理由だけで一方的に離婚を迫ることは、相手方との関係をさらに悪化させ、離婚協議が難航する原因となり得ます。
離婚に際しては、婚姻費用だけでなく、財産分与や慰謝料(離婚原因が相手にある場合)など、他にも解決すべき金銭的な問題が生じます。
これらの条件について夫婦間で合意できなければ、調停や裁判といった法的手続きに移行することになり、時間も精神的な負担も大きくなる可能性があります。
離婚は、単に婚姻費用の支払いから逃れるためだけの手段として考えるべきではありません。
夫婦関係の修復が困難で、将来を見据えた上で双方にとって最善の道であると判断した場合に選択するべきものです。
感情的に結論を出すのではなく、離婚がもたらす生活上・経済上の変化や、子どもへの影響などを総合的に考慮し、冷静に判断することが求められます。
未払いが招く婚姻費用の地獄付け
「婚姻費用の地獄付け」という言葉は、婚姻費用の未払いが引き起こす深刻で困難な状況を比喩的に表現したものです。
具体的には、支払いを怠った義務者が直面する可能性のある様々な不利益や、権利者が被る経済的・精神的な苦痛を指します。
義務者にとって、まず考えられるのは法的な強制力です。
権利者は、調停調書や審判書などの債務名義に基づいて、給与や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行を申し立てることができます。
給与が差し押さえられれば、勤務先に未払いの事実が知られ、社会的な信用を失うリスクがあります。
また、未払い期間に応じて遅延損害金が加算され、支払うべき総額が増大することも少なくありません。
さらに、婚姻費用の不払いは、民法上の「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。
これは夫婦間の扶助協力義務に違反する行為であり、裁判上の離婚原因の一つとなり得ます。
つまり、不払いを続けることで、相手方からの離婚請求が認められやすくなるのです。
権利者側にとっては、婚姻費用の未払いは生活の困窮に直結します。
特に専業主婦(夫)であったり、幼い子どもを抱えていたりする場合、生活費や養育費の確保が困難になり、精神的にも追い詰められる状況に陥ることがあります。
子どもがいる家庭では、その影響は子どもたちの生活や教育にも及びかねません。
このように、婚姻費用の未払いは、法的な問題に留まらず、経済的、社会的、そして精神的な側面で、当事者双方にとって深刻な負の連鎖を生み出す可能性を秘めています。
問題を放置せず、早期に誠実な対応をすることが、このような「地獄付け」とも言える状況を回避するために不可欠です。
婚姻費用問題の解決に向けた交渉術
婚姻費用に関する問題が生じた場合、まずは当事者間での冷静な話し合いによる解決を目指すことが基本です。
感情的な対立を避け、建設的な交渉を進めるためにはいくつかのポイントがあります。
第一に、客観的な資料に基づいて話し合うことが重要です。
双方の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)を開示し、それらを基に婚姻費用算定表などを参考にしながら、妥当な金額の範囲を探ります。
この際、お互いの生活状況や子どもの教育費、医療費といった特別な支出についても具体的に伝え、考慮に入れることが求められます。
第二に、合意内容を明確にすることです。
支払う金額だけでなく、支払い開始時期、支払い期間、支払い方法(振込先の口座情報、毎月の支払日など)についても具体的に取り決め、曖昧さを残さないようにします。
そして、合意した内容は口約束ではなく、書面に残すことが後のトラブルを防ぐ上で非常に有効です。
可能であれば、執行力のある公正証書として作成することで、万が一支払いが滞った場合にスムーズに強制執行の手続きに進むことができます。
第三に、譲歩の精神を持つことです。
自身の主張ばかりを押し通そうとすると、交渉は平行線をたどりがちです。
相手の状況や意見にも耳を傾け、お互いにとって受け入れ可能な着地点を見つける努力が必要です。
もし当事者間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用したり、弁護士に交渉を依頼したりすることも有効な手段です。
調停では、調停委員という中立的な第三者が間に入り、話し合いを円滑に進める手助けをしてくれます。
いずれの方法を取るにしても、相手を尊重し、誠実な態度で交渉に臨むことが、円満な解決への近道となります。
専門家への相談と適切な対応
婚姻費用の問題は、法律的な知識だけでなく、夫婦それぞれの経済状況や生活実態、子どもの有無など、多くの要素が複雑に絡み合って判断されるため、当事者だけでの解決が難しい場合があります。
そのような場合には、弁護士などの法律専門家に相談することが有効な手段となります。
専門家に相談する最大のメリットは、法的な観点から的確なアドバイスを受けられることです。
自身の状況において、婚姻費用を請求できるのか、あるいは支払う必要があるのか、その場合の適正な金額はどの程度かなど、具体的な見通しを得ることができます。
また、相手方との交渉を代理で行ってもらうことも可能です。
感情的になりがちな当事者間の話し合いを、専門家が冷静かつ論理的に進めることで、円滑な合意形成が期待できます。
万が一、話し合いで解決しない場合には、調停や審判といった法的手続きの代理も依頼でき、手続きの負担や精神的なストレスを大幅に軽減することができます。
弁護士を選ぶ際には、離婚や男女問題といった家事事件の取り扱い経験が豊富であるかを確認することが重要です。
また、相談のしやすさや説明の分かりやすさなど、自分との相性も考慮すると良いでしょう。
多くの法律事務所では初回相談を無料または比較的低額で行っているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
相談するタイミングとしては、問題が発生した初期の段階や、当事者間の話し合いが行き詰まったと感じた時などが考えられます。
早期に専門家のアドバイスを受けることで、問題が深刻化する前により有利な条件で解決できる可能性が高まります。
婚姻費用の問題は一人で抱え込まず、専門家の力を借りて適切に対応することが、早期かつ円満な解決への道筋となります。
婚姻費用を払わなくていい場合を総括
-
婚姻費用は夫婦の生活維持に必要な費用であり、民法上の分担義務である
-
別居中でも原則として婚姻費用の支払い義務は継続する
-
婚姻費用をもらえない代表例は、請求側が有責配偶者である場合や同居義務違反がある場合である
-
同意のない別居でも、DVや不貞行為など正当な理由があれば婚姻費用は請求できる
-
権利者の実家暮らしや潜在的稼働能力は、婚姻費用算定で考慮されることがある
-
婚姻費用算定表は標準的な目安であり、個別事情により金額は増減する
-
婚姻費用の未払いには、給与等の差し押さえという強制執行のリスクがある
-
婚姻費用の給与差し押さえは、手取り額の2分の1まで可能である
-
過去の未払い婚姻費用は一括請求が可能で、離婚後も請求権は消滅しない
-
未払い婚姻費用の請求権には時効(原則5年または10年)が存在する
-
離婚すれば婚姻費用の支払い義務は原則消滅するが、子の養育費は別途発生する
-
婚姻費用の不払いは「悪意の遺棄」とみなされ、離婚原因となり得る
-
婚姻費用問題の解決には、客観的資料に基づく冷静な交渉が重要である
-
合意内容は書面に残し、可能であれば公正証書にすることが望ましい
-
婚姻費用問題は複雑なため、弁護士など専門家への早期相談が有効である